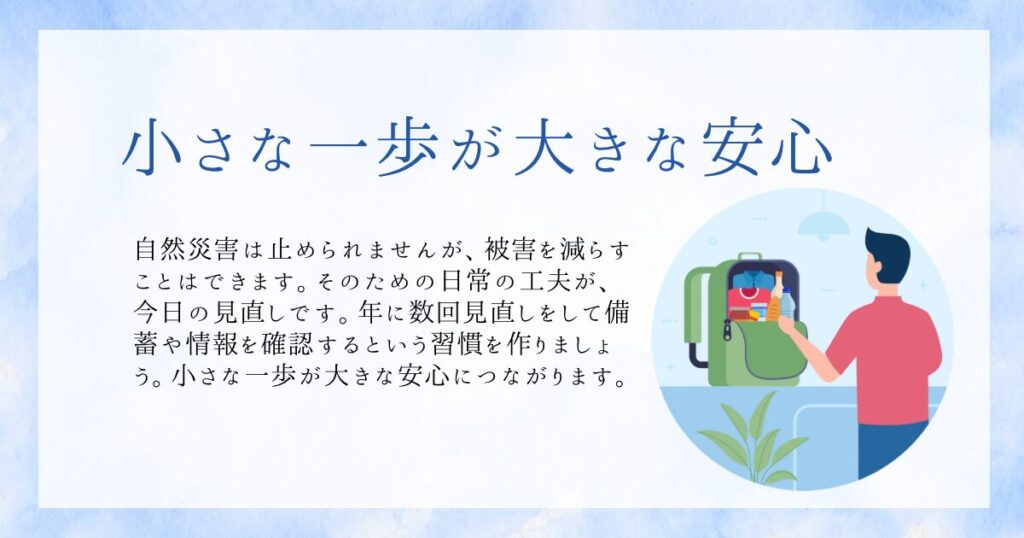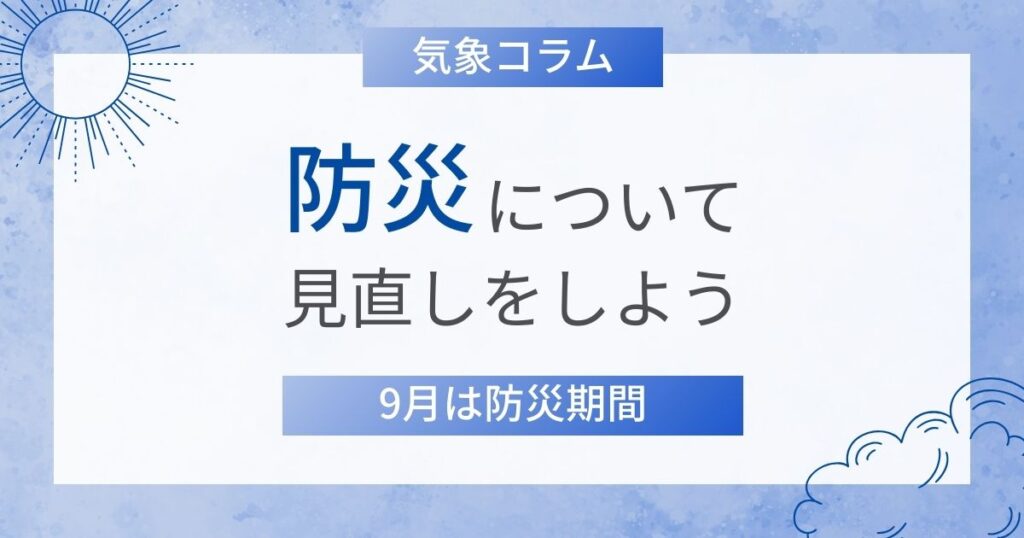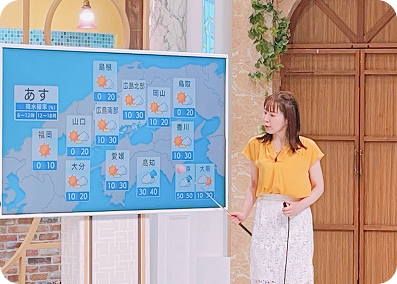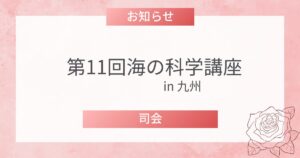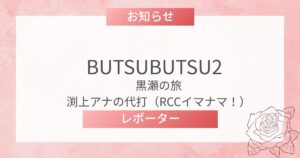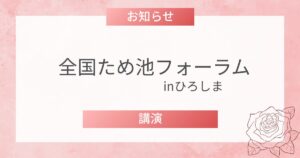なぜ9月が防災月間なの?
9月1日は防災の日、そして9月は防災月間です。
1923年(大正12年)9月1日に10万人以上の死者、行方不明者を出した関東大震災が発生しました。そのことから9月1日を防災の日と制定されました。
また、9月は台風の被害が多い時期でもあるため、防災月間とされています。
二百十日、二百二十日という言葉があり、立春から数えて210日、220日目は台風がきやすい厄日とも昔から言われています。
この機会に、もう一度防災の見直しをしてみませんか?
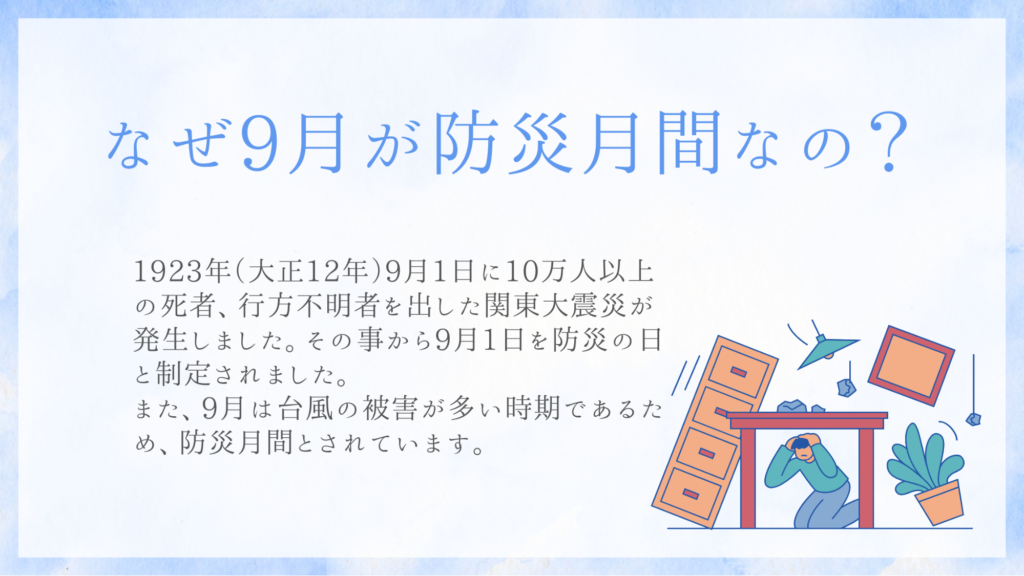
災害の備え、定期的に見直しを
「近年、地震や大雨など災害が多いから何かしら備えをしているよ」という方も多いかもしれません。でも、定期的に見直ししてますか?
備蓄している食料品、賞味期限は切れてないですか?水も賞味期限がありますよ。時折確認して、賞味期限が迫っている物は普段の食事で消費して、新しい物を購入し備蓄する、ローリングストックをしましょう。
災害時に使うランタンや懐中電灯、すぐに使えますか?使おうとしたら、電池が切れていることは実はよくある事です。確認して交換し、更に電池を買い置きしておくと安心です。
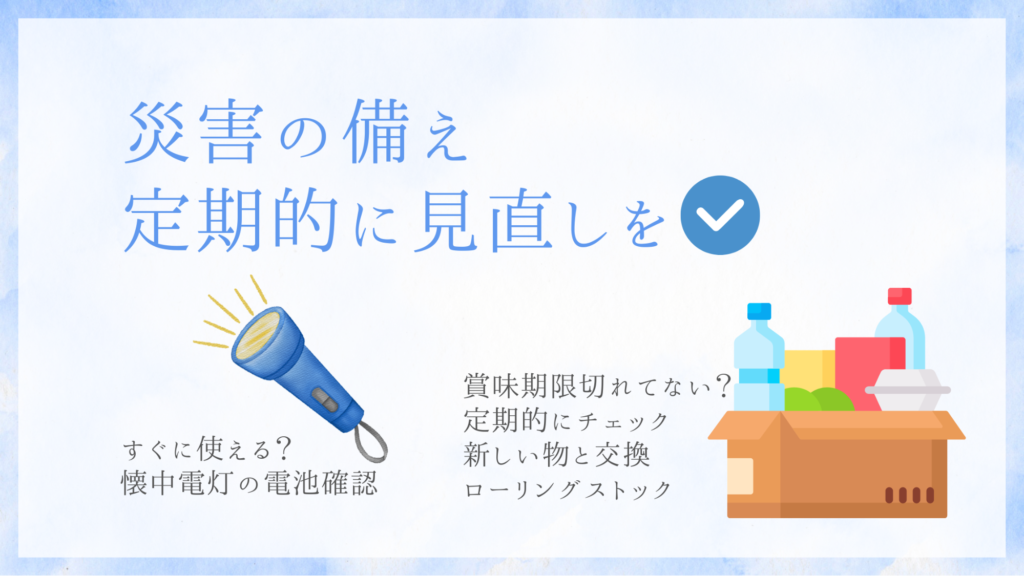
水の備蓄、必要量の目安
水の備蓄は、ライフラインが止まった時の最も大切な必需品です。その目安としては、飲料用と料理用(皿を洗うなどは除き)だけで、1人当たり3リットルの水が必要です。最低3日として、1人9リットルの備蓄が必要です。
家族がもし4人だとしたら?36リットル!私達が思っていたよりもはるかに多い量ですが、準備しておきましょう。
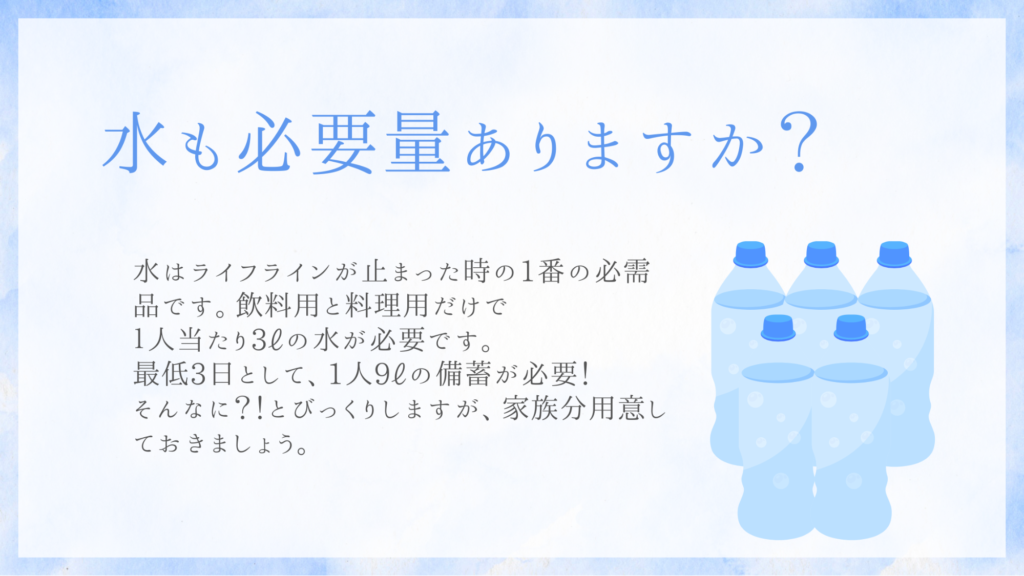
リスク確認を家族で共有
自宅や仕事場の場所は、もし災害が起きた時にどんなリスクがあるのか?川の側だから氾濫する恐れがある、家の裏に斜面があって、大雨の時は土砂崩れが起こる恐れがある。埋立地のため地震の時は液状化が起こりやすいなど、様々だと思います。ハザードマップなどを利用して、リスクを確認し、家族で話し合っておくことが大切です。避難場所はどうするのか?自宅の方が安全なのか?万が一の行動を決めておきましょう。安否確認方法も。避難ルートを歩いてみて、崩れそうな所や足がとられそうな所など、危険箇所がないか確かめておくのも役立ちます。
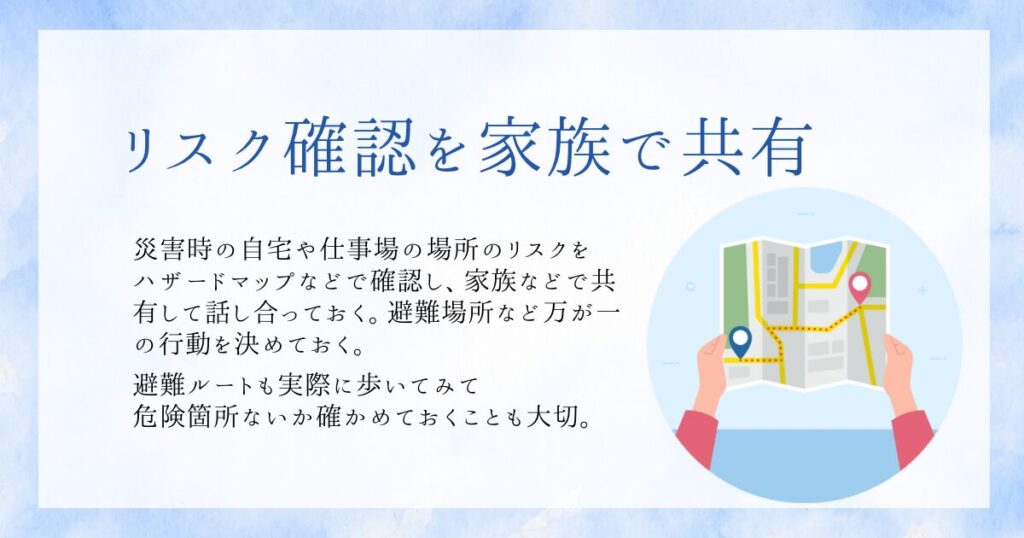
小さな一歩が大きな安心に
私達人間は時折牙をむく自然の脅威には無力で、自然災害は止められません。しかし、その被害を減らすことはできます。そのための日常の工夫が、防災についての見直しです。定期的に見直し、備蓄や情報を再確認する習慣をつけましょう。
忙しい日々の中で忘れがちになりますので、防災月間や防災に触れる機会などを、うまく活用しましょう。一気にできなくてもいいです。気がついた時にこまめにしていきましょう。小さな一歩が大きな安心に繋がりますよ。